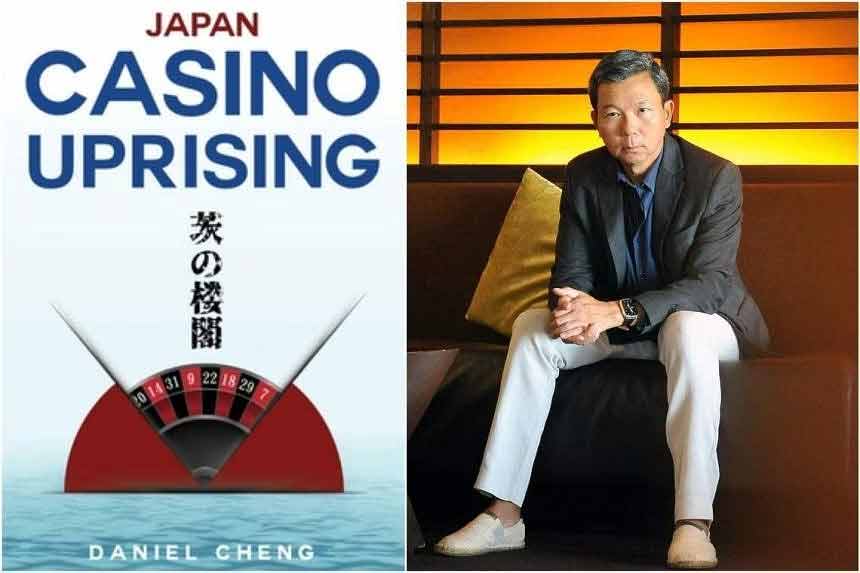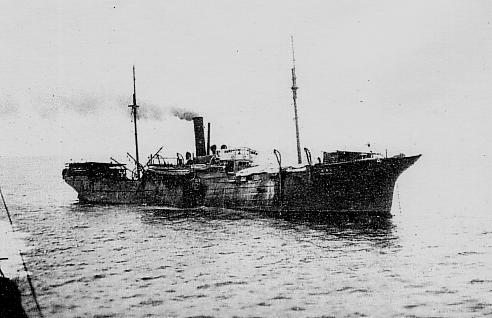多喜二は、私たちになにを語りかけるか
北海道放送、5/31放映予定
作家・小林多喜二の29年4ヶ月の人生をたどるヒューマンドキュメンタリー番組が、HBC(北海道放送)から5月31日(土)、13:05~14:30(道内ローカル)で放送予定です。この番組は、小樽高商・小樽商科大学大創立100年記念として、小樽高商出身小林多喜二をとりあげる85分番組で、HBC制作、そして多喜二の母校・小樽商科大学と白樺文学館多喜二ライブラリーが制作協力しています。
番組タイトルは、「いのちの記憶―小林多喜二・29年の人生」。同番組は、北海道地域での放映ですが、その後、資料編の映像も加えたDVD(2枚組み予定)として、7月中旬~8月下旬に全国発売される予定です。
● 脚本・演出は「東芝日曜劇場」演出の守分さん
脚本・演出を担当されるのは、映像プロデューサーの守分寿男(もりわけ・としお)さん、74歳。
守分さんは、1934年、大分県竹田生まれ。小林多喜二の母校・小樽商科大学を1957(昭和32)年に卒業。開局したばかりの北海道放送(HBC)に入社し、TV番組の制作にあたります。主として東芝日曜劇場のプロデュース・演出にたずさわり、演出作品は『ばんえい』『うちのホンカン』『幻の町』『あかねの空』など多数にのぼります。
同社で常務取締役まで務め、退社された後もフリーの映像プロデューサーとして活躍されています。2004年に木下順二作・劇団民藝公演『巨匠』の演出なども手がけ、近著に、演出家と作家、俳優が紡ぎあげるテレビドラマの制作の裏側をつづった『さらば卓袱台―テレビドラマの風景』(かもがわ出版)があります。
● 制作への発端
氏が同番組の制作に取り組むことになったのは、2004年、小樽商科大学同窓会・緑丘会副理事長の佐野力・白樺文学館館長が守分さんの、緑丘会東京支部での講演を聞き、深く感銘を受けたことに始まります。
小樽商科大学創立100年記念番組として、先輩―小林多喜二の番組を作ってもらいたいという佐野館長の熱烈なオファーに守分さんが快諾。その後、氏の闘病もあり、足かけ5年を要して、このたびの実現となったものです。
この番組では、オホーツクから吹きつける長年の風雪に耐えながら、生きつづける異形の老木の四季の姿を通して、作品は構成されます。
この2月、同大学と白樺文学館共催で行われ、話題となった「蟹工船」読書エッセーコンテスト授賞式の青年たち。2005年の中国・小林多喜二国際シンポジウム(於・河北大学)や、北京・魯迅博物館などの海外取材、北海道、神奈川、東京、奈良、我孫子などでのゆかりの地も取材。
ノーマ・フィールド(米国・シカゴ大学教授)、三浦光世(三浦綾子記念文学館理事長長)などの方々への、「もし多喜二が生きていたら、私たちになにを語りかけるか」のインタビューも撮り終え、現在、編集作業は急ピッチですすめられています。
小樽高等商業学校(小樽商科大学の前身)は北海道の文系の高等教育機関として1911年に、津軽海峡をはさんで本州とは異質の風土、北の商都に開学しました。商業、経済を学ぶ学生ばかりではなく、ひろく文系を志す学生がここに集まりました。小林多喜二は、1921(大正10)年の開学から、10年を迎えた同校に入学しました。一年後には伊藤整も入学してきました。
小樽高商出身の、この二人の文学者の特性を、多喜二のリアリズムと整のリリシズムという対照でとらえ、自然が見せる風土の二面性とともに、大正から昭和のはじめにかけての北海道での剥き出しの資本主義の時代相と重ねあわせて描くドキュメンタリー番組となる予定です。
● これでドキュメンタリーは出来た
小樽商科大学でインタビューを受ける
ノーマ・フィールド教授。右端が守分氏
クリックで拡大
守分さんは、近著『さらば卓袱(ちゃぶ)台―テレビドラマの風景』(2008年2月 かもがわ出版)の「人の風景」の章で、インタビュー中にノーマ・フィールド教授がこぼされた涙について紹介しています。
レポートと語りを引き受けてくれた安藤千鶴子さん(元北海道放送アナウンス部長)にむかって、その目をのぞきこむようにして彼女は言った。
「多喜二さんは、優しい人でした」
多喜二さんは、と語りかけるその口調は暖かく柔らかだった。
多喜二が生涯愛し続けた田口タキは、両親、家族の生活のために酌婦として売られた。その時、まだ十代の半ばを越えたばかりで、なんとかその境遇から抜け出したいと願っていた。
「闇があるから光がある」と多喜二は書き送り、大金五百円を借りて彼女を母親のいる自宅に引きとり、母親もタキを気に入って、これで、と思っていた矢先にタキが家出をしてしまう。
多喜二は泣きながら、小樽の街を探し歩いたという。
ノーマさんは、そのことを話しながら、人間としての多喜二の誠実さに惹かれて、徹底的に多喜二を知ろうと、真冬から春、夏から秋へと変わっていく、小樽での生活を、自ら体験しているのだと言った。
(中略)
多喜二さんが、もし生きていたら、そう言ってノーマさんは沈黙した。長い沈黙であった。沈黙しつづけた。
「多喜二さんは、なによりも平和を願い、弱い立場の人たちのため、私たちの為に、絶対に時代に流されないようにと、メッセージを送ると思います」
思えば、昭和八年(一九三三年)二月二十日、見せしめとして多喜二を殺した国家権力が、わずか十年余りのあいだに日本にもたらしたもの、それは一面の焦土と三百万人を超す死者、そして無惨な敗戦であった。
ふたりの長い沈黙をカメラが捉えつづけた。ノーマさんの目が光り、傍らのバックからハンカチを取り出すと目頭をおさえた。
カットの合図をして、「ありがどうございました」という私の声も涙のために震えていた。
守分さんは、このインタビューで、「これで、このドキュメンタリーは出来た」という実感を得たとつづっています。
小林多喜二が、この世から奪われて75年が経ちます。一世紀近く多喜二の作品がなぜ読まれつづけるのか。多喜二が私たちに遺したものはなんなのか――。
いま、多喜二を愛した人たちの心の中に生きる多喜二を描く同番組は、小林多喜二に新しい生命を与えていくことと思います。
(白樺文学館多喜二ライブラリー学芸員 佐藤三郎)